 |
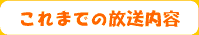 |
| |
 |
| |
|
|
| |
| |
この100年間で地球人口は爆発的に増大し、大気汚染や資源の枯渇などが深刻化してきた。この問題の解決方法の一つとして『火星移住』の研究が進められてきたが、この度『レッドプラネット』という、火星移住をテーマとした映画が公開されることになった。
火星の環境は、地球とどのような点で異なるのか。以下、主な相違点を挙げてみる。
| 1. |
火星の大気は二酸化炭素が95%を占め、動物の生息に不可欠な酸素はほとんど含まれていない。したがって、あらかじめ藻類などの植物を繁殖させて酸素を増やす必要がある。 |
| 2. |
かつて火星に水が存在していたという痕跡がNASAの調査によって判明した。しかしながら、現在のところ、すぐに使える形での水の存在は確認されていない。ただし、極冠の氷には水が含まれているといわれている。 |
| 3. |
火星の平均気温は-50℃以下である。これは、太陽からの距離が地球よりも遠いことと、大気の濃度が地球よりも薄いためである。大気の濃度を高めることは、気温の上昇と宇宙放射線の遮断という2つの観点から不可欠である。 |
火星に移住するためには、上記の居住環境の問題以外にも、最低7ヶ月かかる航行時間にともなう問題などに対処する必要がある。はたして、人類はこれらの難題をどう攻略していくのか。映画のシーンをもとに、惑星科学の専門家による解説を交えて考察していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
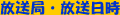 |
|
| |
| |
 |
1/7(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
1/20(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
1/20(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
1/20(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
1/15(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
| |
| |
日本の景況は未だ先行き不透明であるが、それでもほとんどの人が『食べる』ことには困っていないだろう。この『不況にして飽食』という現状を反映してか、近年『食べ放題』の店が繁盛している。しかし、『食べ放題』とはいっても人間には限界があり、その限界にも個人差がある。
我々の口から摂取された物は、食道を経て胃に入るわけだが、当然ながら胃の容量 には限界がある。しかし、通常は限界量に達する前に、視床下部にある満腹中枢によって判断され、食欲がコントロールされる。また、胃に入った物は胃の運動によって十二指腸から小腸へと押し出されるため、これが活発なほど多くの物を食べられることになる。
しかしながら、同じものを食べても太る人とそうでない人がいる。これは先天的な体質の差によるものであるが、生物の進化という観点でいえば、食べても太らない者は淘汰されてきたはずである。つまり、『やせの大食い』は稀であり、飽食の現代において肥満するのは当然なのである。
最近では、肥満に関係する物質の解明も進められており、例えば血液中のたんぱく質『レプチン』が食欲を抑制したりエネルギー消費を高めたりすることが判ってきた。こうした『食』と『体』に関するメカニズムなどを解説していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
| |
乾明夫(神戸大学医学部第二内科助教授)
大阪大学医学部付属病院放射線部 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
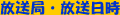 |
|
| |
| |
 |
1/14(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
1/27(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
1/27(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
1/27(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
1/22(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
| |
| |
20世紀の技術革新を象徴するものとして、自動車、航空機、プラスチック、そして『電気』が挙げられるだろう。しかし、いずれもその根底には『石油』が不可欠であった。これまで我々は原料や燃料として大量
の石油を消費してきたが、このまま石油を使い続けると今世紀中には枯渇すると予想されている。さらに、化石燃料を燃やす度に排出される二酸化炭素の存在が無視できない事態となってきたのである。そこで、自然のエネルギーを使い、二酸化炭素を排出しない『グリーン電力』の開発が近年になって急ピッチで進められるようになったのだ。
『グリーン電力』のなかでも特に有望視されているのが『太陽光発電』と『風力発電』である。日本の太陽光発電の導入実績は世界でもトップクラスで、ソーラーパネルの生産に関しては世界一である。一方、風力発電に関してはこれまで導入が遅れていたが、ここ数年でかなり追い付いてきた。しかし、いずれも設備や工事にかかる費用が高く、発電コストも高いため、制度的な後押しが必要な状態である。
太陽光も風力も気候に左右されやすいため、複数の発電方式を組み合わせて電力を確保しなくてはならない。しかしながら、各々についても発電効率を向上させるために、さまざまな研究がなされている。『グリーン電力』がどのように研究されているか、そしてどういった活躍をしているのか、といったことを紹介していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
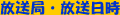 |
|
| |
| |
 |
1/21(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
2/3(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
2/3(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
2/3(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
1/29(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
| |
| |
現代の情報技術を支えるキーワードの一つとして、ノートパソコンや携帯電話に象徴される『機械の小型化』が挙げられるだろう。しかし、我々生物の体は、それらの機械よりもはるかに精巧に創られている。そして、そういった精巧な身体を研究し、治療するためには、『医療機械の小型化』は不可欠である。
『ミクロの決死圏』という映画は、医師がミクロに変身し、血管内を移動して脳を治療するという内容であった。もちろん、実際に人間がミクロに変身することは不可能であり、開発が進められているのは微小なロボットである。体内から治療するロボットが実用化されるまでには、まだかなりの時間が必要だろう。しかしながら、内視鏡にかわるマイクロマニュピレータなど、限定的な検査能力を持ったマイクロサイズの機械は実現に近づいている。また、マイクロマシンが動くために不可欠なのが、微小なアクチュエータ(駆動機)である。これについても研究が進められており、実用化に近づいている。
マイクロマシンを製造する工程にもまた、ミクロの技術が不可欠である。そういった研究の様子や、実用化が近づいているマシンなどを紹介していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
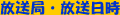 |
|
| |
| |
 |
1/28(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
2/10(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
2/10(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
2/10(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
2/12(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
製作・著作  |
| |