 |
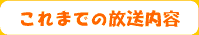 |
| 丂 |
 |
| 丂 |
|
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
丂栰嵷傪怘傋傞偙偲偼寬峃偵椙偄偲偝傟偰偄傞丅偟偐偟丄亀栰嵷亁偵傕偄傠偄傠側傕偺偑偁傞丅僫僗傗僉儏僂儕偼壥
幚傪丄僯儞僕儞偼崻傪怘傋傞傕偺偱偁傞丅僉儍儀僣偼梩傪怘傋傞傕偺偩偑丄梩傪怘傋傞栰嵷偵傕師偺傛偆偵偝傑偞傑側傕偺偑偁傞丅
丂傾僽儔僫壢丗僉儍儀僣丄敀嵷丄彫徏嵷
丂僉僋壢丗儗僞僗丄弔媏
丂傾僇僓壢丗傎偆傟傫偦偆
丂儐儕壢丗偹偓丄偵傜
丂側偐偱傕嬤擭偵側偭偰拲栚偝傟偰偄傞偺偑丄僉儍儀僣傪偼偠傔偲偡傞傾僽儔僫壢偺栰嵷偱偁傞丅 僉儍儀僣偵偼價僞儈儞俠偑懡偔娷傑傟偰偄傞偑丄怘傋偰傕巁枴傪姶偠側偄丅偙傟偼僇儖僔僂儉墫側偳偺宍偱懚嵼偟偰偄傞偨傔偱偁傞丅兝-僇儘僠儞傗價僞儈儞B1丒B2側偳傕懡偔娷傫偱偄傞偑丄嵟傕廳梫側偺偼僉儍儀僣偩偗偵摿偵懡偔娷傑傟傞亀價僞儈儞倀亁偱偁傝丄偙傟偼堓捵釃側偳偺梊杊偵岠壥
揑側暔幙偱偁傞丅
丂 僉儍儀僣偵娷傑傟傞塰梴暘偺岠壥揑側愛傝曽偺傎偐丄嵟嬤偵側偭偰敪尒偝傟偨峈僈儞岠壥 側偳偵偮偄偰傕徯夘偟偰偄偔丅 |
丂 |
|
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
戝捨峩嶰(嫗搒晎棫戝妛嫵庼)
墱揷榓巕(峛撿彈巕戝妛嫵庼)
孁偐偮椏棟愱栧揦亀妶亁
戝憅幚嬈(姅)
偲傫偐偮 偄側偽亀榓岾亁
偍岲傒從偒亀旤廙亁 |
丂 |
|
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
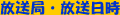 |
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
 |
2/4乮搚乯
|
8丗45乣9丗00
|
| 丂 |
僥儗價榓壧嶳乮WTV乯 |
2/17乮搚乯 |
18丗45乣19丗00
|
| 丂 |
傃傢屛曻憲乮BBC乯 |
2/17乮搚乯 |
18丗45乣19丗00
|
| 丂 |
撧椙僥儗價乮TVN乯 |
2/17乮搚乯 |
17丗00乣17丗15
|
| 丂 |
暉堜僥儗價乮FTB乯 |
2/19乮寧乯 |
16丗00乣16丗15
|
|
| 丂 |
 |
丂 |
|
| 丂 |
|
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
丂嬤擭偵側偭偰丄偟偽偟偽亀儅僀僫僗僀僆儞偑懱偵偄偄亁偲偄偆榖傪暦偔傛偆偵側偭偨丅偟偐偟側偑傜丄偦偺幚懺偵偮偄偰偼丄偁傑傝抦傜傟偰偄側偄傛偆偱偁傞丅
丂嬻婥拞偺拏慺傗巁慺偼丄捠忢側傜揹婥揑偵拞惈偺暘巕偲偟偰懚嵼偡傞丅偟偐偟丄偦傟偼昁偢偟傕埨掕偟偰偄傞傢偗偱偼側偔丄偦偺堦晹偼揹壸傪帩偭偨亀僀僆儞亁偲偟偰懚嵼偡傞丅摿偵丄戧側偳偺傛偆偵悈偑寖偟偔傇偮偐傝崌偆強偱偼丄亀儗僫乕僪尰徾亁偵傛偭偰亀儅僀僫僗僀僆儞亁偑懡偔側偭偰偄傞丅媡偵丄姴慄摴楬偺嬤偔偱偼丄暡恛偺塭嬁偱僾儔僗僀僆儞偺曽偑懡偔側傞丅傑偨丄幒撪偱傕僞僶僐偺墝傗揹帴攇側偳偺塭嬁傪庴偗傞忬嫷偱偼儅僀僫僗僀僆儞偑彮側偔側傞丅
丂 偝偰丄亀儅僀僫僗僀僆儞亁偼側偤懱偵偄偄偺偩傠偆偐丅惗懱撪偺愒寣媴偼丄昞柺 偵儅僀僫僗偺揹壸傪懷傃偰偍傝丄屳偄偵寢崌偟側偄傛偆偵側偭偰偄傞丅偲偙傠偑丄亀妶惈巁慺亁偺摥偒偵傛偭偰揹巕傪扗傢傟傞偲丄偙偺惈幙偑幐傢傟偰丄偦偺寢壥
丄寣塼偺擲搙偑憹偡偺偩丅偦偙偱丄亀儅僀僫僗僀僆儞亁傪庢傝擖傟偰丄妶惈巁慺偺摥偒傪拞榓偡傞昁梫偑惗偠偰偔傞丅偟偐偟丄愭弎偺傛偆偵丄暡恛傗揹帴攇偺塭嬁傪庴偗傞娐嫬偱偼亀儅僀僫僗僀僆儞亁偑晄懌偟偰偟傑偆偨傔丄儅僀僫僗僀僆儞傪敪惗偡傞僌僢僘側偳偑昁梫偲側偭偰偄傞偺偱偁傞丅
丂奺娐嫬偛偲偺僀僆儞擹搙應掕傗丄儅僀僫僗僀僆儞傪梺傃傞慜屻偺寣棳傗寣摐抣側偳偺斾妑丄偝傜偵丄亀儅僀僫僗僀僆儞亁傪梡偄偰傾僩僺乕惈旂晢墛傪帯椕偡傞帋傒側偳傪徯夘偟偰偄偔丅 |
丂 |
|
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
|
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
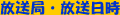 |
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
 |
2/11乮搚乯
|
8丗45乣9丗00
|
| 丂 |
僥儗價榓壧嶳乮WTV乯 |
2/24乮搚乯 |
18丗45乣19丗00
|
| 丂 |
傃傢屛曻憲乮BBC乯 |
2/24乮搚乯 |
18丗45乣19丗00
|
| 丂 |
撧椙僥儗價乮TVN乯 |
2/24乮搚乯 |
17丗00乣17丗15
|
| 丂 |
暉堜僥儗價乮FTB乯 |
2/26乮寧乯 |
16丗00乣16丗15
|
|
| 丂 |
 |
丂 |
|
| 丂 |
|
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
丂20悽婭偺媄弍妚怴偼丄尷傝偁傞帒尮傪楺旓偟偰丄戝検 偺攑婞暔傪惗傒弌偡偙偲偵傛偭偰惉傝棫偭偰偒偨偲傕偄偊傞丅偟偐偟側偑傜丄崚暔偐傜惗暘夝惈庽帀傪嶌傞尋媶側偳偑恑傒巒傔偨丅崱夞偼丄屆巻偐傜栘嵽傪嶌傞尋媶偵偮偄偰徯夘偡傞丅
丂栘傪峔惉偡傞暔幙偵偼丄慇堐亀僙儖儘乕僗亁偲丄偦傟傪愙拝偝偣傞暔幙亀儕僌僯儞亁偑偁傞丅栘偐傜巻傪嶌傞嵺丄僙儖儘乕僗偼嵽椏偲偟偰昁梫偩偑丄儕僌僯儞偺曽偼晄梫暔偲偟偰幪偰傜傟偰偄傞偺偩丅媡偵丄巻偐傜栘嵽傪嶌傞応崌丄巻偐傜惛惢偟偨僙儖儘乕僗偵儕僌僯儞傪壛偊傞昁梫偑偁傞丅偙偺曽朄偱嶌傜傟偨亀栘嵽亁偼丄師偺傛偆側摿挜傪帩偭偰偄傞丅
| 1. |
捠忢偺栘嵽偲摨偠傛偆偵丄嶍偭偨傝揃傪懪偮偙偲偑偱偒傞偲偄偆丅偨偩偟丄惢朄傪岺晇偟側偗傟偽丄崌斅偺傛偆偵峝偔丄壛岺偟偵偔偔側傞丅 |
| 2. |
捠忢偺栘嵽偲偼堎側傝丄宆榞偵偼傔偰惉宍偡傞偨傔丄暋嶨側宍偺傕偺傪検 嶻偱偒傞丅 |
| 3. |
捠忢偺栘嵽偲偼堎側傝丄擭椫偑懚嵼偟側偄丅偨偩偟丄壛岺偺夁掱偱柾條傪擖傟傞偙偲偼壜擻丅 |
| 4. |
捠忢偺栘嵽偲摨偠傛偆偵丄搚偵曉偡偙偲偑偱偒傞丅 |
丂幚嵺偵彜昳壔偡傞偨傔偵偼丄惢巻夁掱偱儕僌僯儞傪幪偰偢偵拪弌偡傞曽朄偑妋棫偝傟側偔偰偼側傜側偄丅偟偐偟側偑傜丄亀栘喬巻亁弞娐偵岦偗偨婱廳側惉壥
偱偁傞偙偲偼妋偐偩傠偆丅幚嵺偵巻偐傜栘嵽偑偱偒傞條巕側偳傪徯夘偟偰偄偔丅 |
丂 |
|
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
鋞壀惓岝(嶰廳戝妛嫵庼)
墹巕惢巻
椦栰挕怷椦憤崌尋媶強 |
丂 |
|
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
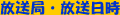 |
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
 |
2/18乮搚乯
|
8丗45乣9丗00
|
| 丂 |
僥儗價榓壧嶳乮WTV乯 |
3/3乮搚乯 |
18丗45乣19丗00
|
| 丂 |
傃傢屛曻憲乮BBC乯 |
3/3乮搚乯 |
18丗45乣19丗00
|
| 丂 |
撧椙僥儗價乮TVN乯 |
3/3乮搚乯 |
17丗00乣17丗15
|
| 丂 |
暉堜僥儗價乮FTB乯 |
3/5乮寧乯 |
16丗00乣16丗15
|
|
| 丂 |
 |
丂 |
|
| 丂 |
|
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
丂偙偙悢擭亀僔僱儅僐儞僾儗僢僋僗亁偲屇偽傟傞暋崌宆塮夋娰偑慡崙奺抧偵嶌傜傟傞傛偆偵側偭偨丅偦偺堦偮丄搶峀搰偵抋惗偟偨僔僱僐儞亀俿僕儑僀搶峀搰亁偵丄彜梡偲偟偰偼悽奅偱弶傔偰亀DLP僔僱儅僔僗僥儉亁偑摫擖偝傟偨偺偱偁傞丅
丂亀DLP亁偲偼丄亀Digital Light Processing亁偺棯偱偁傝丄偦偺柤偺偲偍傝丄岝偺恑楬傪僨僕僞儖惂屼偡傞僔僗僥儉偱偁傞丅偦偺拞怱偲側傞偺偑亀DMD亁(Digital
Micro-mirror Device)偲偄偆岝敿摫懱偩丅偙傟偼丄16兪m妏偲偄偆旝彫側嬀傪暲傋偨傕偺偱偁傝丄偦偺奺乆偺妏搙傪曄偊傞偙偲偵傛偭偰丄岝傪幷抐偟偨傝斀幩偟偨傝偡傞傕偺偱偁傞丅
丂DLP僔僗僥儉傪梡偄傞偲丄廬棃偺僾儘僕僃僋僞乕傛傝傕偼傞偐偵慛柧側塮憸偑嶌傝弌偣丄柧傞偄応強偱傕塮憸傪幨 偟弌偡偙偲偑壜擻偲側傞丅偟偐傕丄僾儘僕僃僋僞乕偼僐儞僷僋僩偱帩偪塣傃傗偡偄丅偟偐偟丄偙偺僔僗僥儉偺嵟戝偺晲婍偼丄塮憸傪揹攇偱攝怣偟丄僼傿儖儉傪巊傢偢偵丄塮夋偺悽奅摨帪岞奐偑壜擻偵側傞偙偲偱偁傞丅塮夋奅傪戝偒偔曄偊傞壜擻惈偺偁傞亀DLP亁偺枺椡傗巇慻傒側偳傪徯夘偟偰偄偔丅 |
丂 |
|
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
|
丂 |
| 丂 |
 |
丂 |
| 丂 |
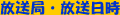 |
丂 |
| 丂 |
| 丂 |
 |
2/25乮搚乯
|
8丗45乣9丗00
|
| 丂 |
僥儗價榓壧嶳乮WTV乯 |
3/10乮搚乯 |
18丗45乣19丗00
|
| 丂 |
傃傢屛曻憲乮BBC乯 |
3/10乮搚乯 |
18丗45乣19丗00
|
| 丂 |
撧椙僥儗價乮TVN乯 |
3/10乮搚乯 |
17丗00乣17丗15
|
| 丂 |
暉堜僥儗價乮FTB乯 |
3/12乮寧乯 |
16丗00乣16丗15
|
|
| 丂 |
 |
丂 |
|
惢嶌丒挊嶌  |
| 丂 |