 |
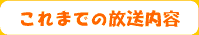 |
| |
 |
| |
|
|
| |
| |
日本人の4割近くが近視であり、これまでにも視力矯正に関するさま ざまな方法が提唱されてきた。しかしながら、これまでの視力矯正方法
はいずれも効果が疑わしいものであり、一般的には「近視は治らない」 とされてきた。ところが、レーザーを用いた治療法が昨年に日本でも認
可されてから、スポーツ選手をはじめとする多くの人が視力を回復する ようになった。
そもそも、近視とは角膜の屈折率が強すぎて網膜の手前でピントが合 ってしまう状態を指している。したがって、レーザーで角膜の形を変え
ることで焦点を合わせることが可能である。治療に用いられるレーザー は「エキシマレーザー」というもので、もともとはコンピュータなどの
精密な部品の製造に使われていたものである。つまり、精密なレーザー 照射技術が確立するまでは、こういった治療は不可能であったわけであ
る。この「エキシマレーザー」を用いた治療法のうち、角膜表皮をめく ってから、角膜を削った後、表皮を元に戻す「LASIK」という治療
法が、現在最も注目されている。
「LASIK」もまた、外科手術である以上リスクがまったく無いわ けではないが、手術時間は15分程度で痛みも少なく、欧米では50万人が
「LASIK」によって視力を回復しているのである。実際に「LAS IK」がどのような手順で行なわれるかを紹介するとともに、手術を受
けるための条件なども解説する。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
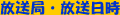 |
|
| |
| |
 |
3/4(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
3/17(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
3/17(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
3/17(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
3/19(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
| |
| |
日本における自動販売機の普及台数は約560万台でアメリカに次いで世界第2位 、人口比では世界一である。そして、この数はなんと公衆電話の約8倍に相当するという。これだけ多くの自販機が日本で普及した背景として、治安の良さなどが挙げられるが、やはり「便利さ」と「製造技術」が最大のポイントとなるだろう。
日本で最初に実用化された自動販売機は、明治37年に俵谷高七によって開発された「自働郵便切手葉書売下機」である。それから約100年の間にさまざまな自販機が作られ、現在では喫茶店さながらの性能を持ったカップ式自販機などが見られるようになった。そこには、コンパクトな機械内でコーヒー豆を挽く技術や、砂糖・クリームの量
を調節する機能、さらには注入する湯の適温を保つ技術などが凝縮されているのだ。これらの操作が実際にどのように行なわれているか、自販機メーカーの協力によって撮影することができた。
最近になっても、自販機を非常時の備蓄庫として利用する試みや、深夜電力を利用した「エコベンダー」、ITを駆使した在庫管理システムなど、自販機は進化を続けている。こうした自販機の近況なども紹介していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
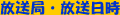 |
|
| |
| |
 |
3/11(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
3/24(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
3/24(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
3/24(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
3/26(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
| |
| |
今やさまざまなところで見られるようになったコンピュータグラフィックス(CG)だが、最初から必ずしも現在のような利用法が想定されていたわけではない。
民間でのCG制作は80年代前半に始まったが、当時は制作環境をすべて手作りで整える必要があり、1日で作れるCGの量も非常に少なかった。そのため、制作費は1秒あたり50万円以上となり、コマーシャル以外には使えない状況であった。また、建築などの分野で「ワイヤフレーム」という、線だけで描かれたCGが用いられていたが、これには、面を描くよりも計算時間が短くてすむ、というメリットがあった。
やがて、映像としての質が向上するとともに、CGが使われる分野が広がってきた。アメリカでは映画において実写背景と融合させる形でのCGが発展したが、日本ではむしろコンピュータゲームがその主導的な役割を果たしてきた。90年代になって急速に増えた三次元の映像表現は、それまでのゲームにはなかった要素を取り入れることを可能とし、とりわけ人物の動きの表現に関しては海外でも高い評価を得ているのだ。
このほか、CGに欠かせない「科学シミュレーション」のことや、フルCG映画の試みなどについて解説していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
| |
リンクス・デジワークス
バス・プラスワン
ソニー・コンピュータエンターテインメント
スクウェア
カプコン
ポリゴンピクチュアズ
資生堂 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
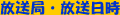 |
|
| |
| |
 |
3/18(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
3/31(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
3/31(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
3/31(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
4/2(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
| |
| |
「アイボ」をはじめとするペット型ロボットが流行しているが、その形状や機能はさまざまである。人々はこうした「ロボットペット」に何を求めているのだろうか。
ロボットペットの機能と役割を考えるうえで欠かせない点は次の通 りである。
| |
(1)小型化: |
家庭内で動かせる大きさでなくては、共生は不可能である。 |
| |
(2)センサー: |
ロボットペットの多くは、光や音、障害物などを感知する機能を持っている。 |
| |
(3)人工知能: |
ロボットペットの多くは、感知した情報に応じて、どのような行動をとるか、自律的に判断することができる。 |
とりわけ、「センサー」と「人工知能」のレベルによって価格や役割が大きく変わってくる。音に反応して走りだすだけの単純なものと、複数のセンサーと記憶能力を持ち、ペットのように育てることができるものでは、所有者の思い入れも異なるだろう。特に「アイボ」のような高性能のロボットペットになると、家族の一員のように可愛がる人も少なからず存在するのである。
このほか、声に反応していろいろな言葉を話すロボットや、携帯型ゲーム機で行動ルーチンをプログラミングできる昆虫形ロボット、太陽電池によって水槽を泳ぐロボットなどを紹介していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
| |
大塚純子(アイボ愛好家)
ソニー
タカラ
バンダイ
トミー |
|
|
|
| |
 |
|
| |
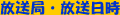 |
|
| |
| |
 |
3/25(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
4/7(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
4/7(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
4/7(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
4/9(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
製作・著作  |
| |