 |
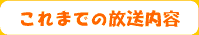 |
| |
 |
| |
|
|
| |
| |
日本で自然に咲いている花の1/3が黄色であるが、蝶や蜂などの昆虫は黄色が好きだという。実際にさまざまな色の皿に洗剤入りの水を注ぎ、一晩置いておくと、黄色の皿に虫が多くたまっていた。
ミツバチは赤色を見ることはできず、黄色から紫外線までを見ることができる。黄色い花を特殊なカメラで見ると、花びらに紫外線を反射する部分があることがわかる。この模様は『蜜標』という、昆虫を花粉のあるところへ導くサインである。また、黄色以外の花であっても花粉は黄色であり、そこへ昆虫が導かれるようになっている。
ところで、花びらが黄色くなる仕組みについても研究が進んでいる。キンギョソウの花を黄色くしているのは「オーロン」という物質であるが、これを作り出す酵素が最近になって発見された。その酵素を用いれば、ペチュニアなど本来黄色にならない花でも、黄色の花を咲かせるようにすることが可能になるという。
このほか、白い花を使って染色すると淡い黄色に染まるという話など、「黄色」を中心とした「花の色」について紹介していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
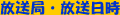 |
|
| |
| |
 |
5/5(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
5/12(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
5/12(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
5/12(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
5/14(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
| |
| |
核家族化や高度情報化によって人間関係の希薄になってきた。
そこでペットに「癒し」を求める人が増えてきたが、どのように飼われているのだろうか。
「犬」や「猫」といった定番以外に、最近では爬虫類やハムスター、プレーリードッグなどの需要が増えている。これらは、鳴き声の心配をしなくてよいという利点があり、特にプレーリードッグの場合は知能もそこそこ高く、人間になつきやすい点も好評である。
一方、ペットの住環境も大きく変化してきた。ヘーベルハウスの「プラスわん」「プラスにゃん」は人間とペットが共生することを目的とした住宅であり、ペットが自由に動けるような設計がなされている。また、ペットフードについても改良が進められ、栄養満点で美味なものが多くなっている。
しかしながら、ペットを過剰にかわいがることによって、そのペットが病気になってしまうケースも多発している。栄養豊富なペットフードの食べ過ぎによる肥満や、ペットの気分を無視した接触によるストレスなどで病院に運び込まれるような事態になるのだ。
動物の習性を理解し、適度な距離を保つことも大切なのである。番組では、こうした「ペット」に関わるさまざまな事象を紹介していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
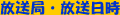 |
|
| |
| |
 |
5/12(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
5/19(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
5/19(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
5/19(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
5/21(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
| |
| |
睡眠中の「いびき」は、周囲の人にとっては気になるが、本人には自覚がない。そして、一見「気持ちよさそうに寝ている」ようであるが、過度の「いびき」というのは、実はかなり危ない「病気」なのである。
我々が眠っているとき、軟口蓋に舌が下がって気道が狭くなるのだが、これが極端に狭くなると、呼吸時の抵抗が大きくなり、「いびき」が発生しやすくなる。なかでも重度の場合は、しばらく呼吸が止まったり、突然吸い上げるような激しい「いびき」が発生したりする。この症状を「睡眠時無呼吸症候群」とよび、彼らが心筋梗塞や脳卒中になる確率は通
常の5倍ともいわれている。また、眠りが浅い状態が続いているので、昼間でも眠気が襲ってくることも多いのだ。
睡眠時無呼吸症候群の主因のひとつに「肥満」が挙げられるが、要するに気道を広く保つことが大切である。「スリープスプリント」というマウスピースを装着し、下あごを前に出すことで気道を確保するという方法があり、実際に「いびき」がかなり軽減されることが確認されている。また、豪州で開発された「CAPA療法」という治療法が効果
をあげているという。この最新の治療法についても紹介していく。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
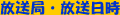 |
|
| |
| |
 |
5/19(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
5/26(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
5/26(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
5/26(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
5/28(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
| |
|
|
| |
| |
日本で最も多くの人がかかっている病気は「虫歯」と「歯周病」である。
また、近年になって「不正咬合」などについても注目されるようになってきた。
虫歯は、食べかすに含まれる糖質が「ストレプトコッカス・ミュータンス」などの細菌によって歯垢に変えられ、酸化によって歯の組織が破壊されることで進行する。したがって、糖質がなければ歯垢はできないし、無菌状態だと「虫歯」にはなり得ない。また、唾液のPHが高ければ「虫歯」は進行しにくく、たとえば「猫」は唾液のPHが高いため「虫歯」になりにくいという。「歯周病」もまた、歯垢に潜む細菌の出す毒素によって歯周組織が破壊されることで進行する。
しかしながら、その原因となる菌の種類は「虫歯」よりもはるかに多く、300種に及ぶといわれている。
歯が抜けた場合、これを放置しているとその両隣や相対する歯がずれやすくなり、全体の噛み合わせに影響が生じる。歯並びや噛み合わせが悪いと、発声が悪くなるほか、頭痛や肩こりなど全身に影響が生じる。しかしながら、現代人の顎は年を追うごとに細くなっており、「歯並び」が悪くなっているのが現状である。そういうわけで「歯科矯正手術」のニーズが高まっているが、矯正具を装着している間にも生活を続けるため、その見栄えを良くする工夫が為され始めた。
ともかく、大切な歯を守る最良の方法は「歯みがき」である。最近では高性能の「音波振動歯ブラシ」も発売されており、これについても番組の最後に紹介する。 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
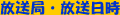 |
|
| |
| |
 |
5/26(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
6/2(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
6/2(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
6/2(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
6/4(月) |
16:00〜16:15
|
|
| |
 |
|
|
製作・著作  |
| |