| |
|
|
| |
| |
楽器の鳴らし方にもいろいろあるけど、『吹奏楽』の場合、特に『吹く』楽器が主役。
今回は、そんな『吹く』楽器について、どうして演奏できるのか、教えちゃうのだ!
−解説した内容− |
|
| |
| (1) |
音程のはっきりした『音』を鳴らすためには、空気を安定的に振動させる必要がある。
管楽器の場合、その『音源』は三種類に大別できる。
| 1. |
リードとよばれる薄い板を振動させるもの。 |
[クラリネット,
オーボエ] |
| 2. |
くちびるを安定的に振動させるもの。 |
[ホルン,
トランペット] |
| 3. |
気流の衝突から安定的な振動を作るもの。 |
[フルート,
リコーダー] |
|
| (2) |
昔から知られている『草笛』は、オーボエと同じ仕組みである。
そして、どこにでもある『ストロー』でも同様に音を鳴らすことができる。 |
| (3) |
管の長さが半分になれば、その音は『1オクターブ』高くなる。
また、管そのものの長さを変えなくても、途中に穴を開ければ同じ効果が得られる。リコーダーなどは、『穴の開閉』によって実質的には『管の長さ』を変えていることになる。 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
| |
神谷徹(ストロー楽器奏者)
大阪音楽大学
ドルチェ楽器 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
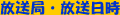 |
|
| |
| |
 |
12/22(土)
|
8:45〜9:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
12/29(土) |
18:45〜19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
12/29(土) |
18:45〜19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
12/29(土) |
17:00〜17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
1/5(月) |
7:15〜 7:30
|
|
| |
 |
|