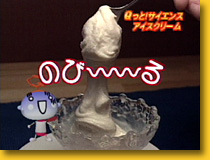|
|
|
| |
| |
そよかぜでも空高く舞い、トンビが鳥と間違えて攻撃してくる。
これまでの『凧』とはぜんぜんちがう飛びかたをする『バイオカイト』について紹介するよ!
-Qっとくんが理解したこと- |
|
| |
| (1) |
『和凧(わだこ)』などの場合、風に『押される』ことで浮き上がる。
だから、これまでの『たこあげ』は、強い風が吹く、冬の遊びだった。
ところが、『バイオカイト』の場合は、飛行機やグライダーと同じしくみで浮き上がるので、弱い風でもまるで鳥のようにまいあがるのだ。 |
| (2) |
強い風が吹くところで遊ぶ『和凧』は、こわれにくいように丈夫に作られている。
『バイオカイト』は軽い材料を使っているのだが、実は強い風が吹いてもこわれないような『しかけ』がある。翼(つばさ)にあたる部分に『バネ』のしくみを持たせることで、『はばたいて』力を逃がすようになっているのだ。
こうしたことによって、糸も『ミシン糸』や『つり糸』のような細いものが使えるようになっている。 |
| (3) |
生き物のような形をしていることから『バイオカイト』と名づけられているが、要するに『左右対称(さゆうたいしょう)』で、飛行機のように『主翼(しゅよく)』と『尾翼(びよく)』があれば、ちゃんとまいあがるのだ。 |
|
|
| |
-プラスあるふぁ- |
|
| |
 |
『バイオカイト』は、完成品ではなく『キット』として売られており、自分で組み立てるようになっている。組み立てながら『飛ぶための構造』を学ぶことができるので、理科教材としても薦められるのだ。 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
伊藤利朗(バイオカイト開発者)
森久エンジニアリング
http://www.biokite.com/ |
|
| |
 |
|
| |
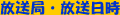 |
|
| |
| |
 |
5/25(土)
|
9:45~10:00
|
| |
テレビ和歌山(WTV) |
6/1(土) |
18:45~19:00
|
| |
びわ湖放送(BBC) |
6/1(土) |
18:45~19:00
|
| |
奈良テレビ(TVN) |
6/1(土) |
17:00~17:15
|
| |
福井テレビ(FTB) |
6/3(月) |
16:00~ 16:15
|
|
| |
 |
|