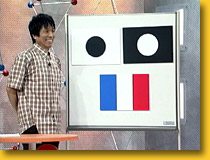| |
『天気予報』や『カーナビ』などに欠かせない『人工衛星』。
でも、どうして地球の周りを回りつづけられるの?
今回は、人工衛星のしくみと役割について解説するよ!
-Qっとくんが理解したこと- |
|
| |
| (1) |
人工衛星(じんこうえいせい)が地球のまわりを回りつづけられるのは、速いスピードで動く衛星の『遠心力(えんしんりょく)』と、地球の『引力』がつりあっているからである。引力とつりあうためには、時速28,000kmという、ものすごいスピードを出さないといけないのだ。 |
| (2) |
人工衛星の回りかたには、地球から見て常に同じ位置にある『静止(せいし)衛星』と、回りながら地球の反対側も観測(かんそく)できる『移動衛星』がある。例えば、気象衛星『ひまわり』や放送衛星などは『静止衛星』、地球全体の大気や水の循環(じゅんかん)を調べる観測衛星は『移動衛星』の代表的なものといえる。 |
| (3) |
今年の秋に打ち上げられる観測衛星『ADEOS-Ⅱ』には、『エルニーニョ現象』など、地球全体に影響(えいきょう)がある水の動きや温度変化を調べ、環境(かんきょう)変化のメカニズムを知る材料になることが期待されているのだ。 |
|
|
| |
-プラスあるふぁ- |
|
| |
 |
地球全体の降水量や温度変化などを調べる観測衛星、たとえば『TRMM』や『ADEOS-Ⅱ』のようなものは、すべての観測地点をなるべく同じ条件で調べる必要がある。したがって、観測地点の太陽時刻が常に等しくなるような軌道(TRMMの場合、常に10時30分)で回らなくてはならない。
こうした軌道で回る人工衛星を『太陽同期軌道衛星』という。 |
|
|
| |
|
|