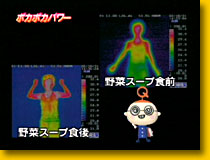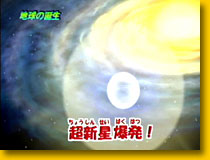| |
私たち人類をはじめ、さまざまな生物がすむ『地球』。
このすばらしい惑星は、いったいどのようにして創られたのだろうか。
そんな『地球の誕生』に関する不思議を、解説しちゃうぞ!
−Qっとくんが理解したこと− |
|
| |
| (1) |
地球は、およそ46億年前に誕生した。もう少しこまかくいえば、地球の『材料』が太陽系の誕生とともに作られたのが46億年前であり、『地球』という1個の天体として固まるまでに、それから1億年ほどかかったと考えられている。このような『いつ誕生したか』を知るには、
隕石(いんせき)を調べる必要がある。小惑星帯(しょうわくせいたい)から飛んできた隕石は、地球とほぼ同時に作られ、その状態を保っている。
したがって、『放射性元素(ほうしゃせいげんそ)』という、時間とともに減っていく物質が隕石の中にどれだけ残っているかを調べれば、その隕石がいつ作られたか、つまり隕石と同時に作られた地球の誕生した時期がわかるのだ。 |
| (2) |
『超新星爆発(ちょうしんせいばくはつ)』は、星の最期であると同時に新たな星の誕生へ向けての第一歩でもある。『超新星爆発』によって、さまざまな元素がばらまかれ、ガスの雲が形成されるが、ところどころでガスが集まり、『微惑星(びわくせい)』という『石のかたまり』がたくさんできたのだ。この『微惑星』どうしがぶつかり合い、しだいに大きくなって、熱い『原始地球』というものになった。『原始地球』はマグマの集まりであったが、重い『鉄』などは沈んで『核(かく)』となり、表面は冷えて『地殻(ちかく)』となり、現在のような『地球』ができあがったのだ。 |
| (3) |
地球が他の惑星、たとえば『金星』や『火星』などと異なるのは、陸と海があり、場所ごとに環境が異なるという『多様性』である。
こうした『多様性』があるからこそ、気候のバランスを保て、さまざまな種類の生物が存在できるのだ。 |
|
|
| |
−プラスあるふぁ− |
|
| |
 |
 |
宇宙に数多ある惑星の多くは、太陽系の惑星と同じような過程を経て作られたと考えられる。したがって、地球と同じような環境を持ち、生命活動のある惑星は少なからず存在すると推測されている。
生命存続のための条件は多数あるが、そのいくつかを以下に挙げる。 |
| |
・ |
恒星からの距離が近すぎると、金星のような『二酸化炭素に包まれた熱い星』になる。遠すぎると『凍りついた星』になると考えられるが、その距離の許容範囲は案外広く、火星でも(距離的には)生命は存続し得るという。 |
| |
・ |
惑星が小さすぎると、引力および地磁気が弱く、生命存続のために必要な 大気が残らない。大気は放射線の影響を軽減するために不可欠である。
火星についても、距離ではなく大きさが不適当だったという見方がある。 |
|
|
| |
|
|