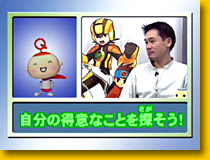| |
みんなは、どんな遊びをするのかな? 『コンピューターゲーム』ってひとも多いよね。
今回は、人気のゲームがどのようにしてつくられるか、『ゲームクリエイター』がどんなことをしてるのか、などなど紹介しちゃうぞ!
-Qっとくんが理解したこと- |
|
| |
| (1) |
多くの人が協力してゲームを作っているが、『ゲームクリエイター』の仕事は、次のように大きく4つに分けられる。
(ゲームプランナー)
『どんなゲームを作るのか』を考える人。
操作方法やシナリオなどを考え、それを他のスタッフに伝える。
(グラフィックデザイナー)
ゲームの『絵』を考え、描く人。キャラクターはもちろん、 背景やアイコンなど、さまざまなものを描く必要がある。
(サウンドクリエイター)
ゲームの『音』を考える人。テーマ曲やBGMだけでなく、ファンファーレや効果音など、さまざまな音が必要。
(プログラマー)
ゲームが実際に動くように、プログラムを組む人。コンピューターによる処理の順序を工夫することで、ゲームの動きが大きく変わる場合もある。 |
| (2) |
みんなに受け入れられやすいゲームを作ろうとすれば、キャラクターの姿や動きは『身の回りにあるもの』をもとに作るのがふつうである。
姿については、身近な動物の特徴をいくつか合わせたものがよく使われる。
動きは、普段の『走る』『投げる』などの行動がキーになるのだ。 |
| (3) |
『ゲームクリエイター』になるためには、まず自分に『何ができるか』を知ることが大切である。そのうえで、得意なことの周辺にあるさまざまなものに接し、広い視野を持つことが必要である。
また、ゲームは多くの人が協力して作るので、『仲間とのコミュニケーション』も大切な要素なのだ。 |
|
|
| |
-プラスあるふぁ- |
|
| |
 |
家庭用ゲーム機で表現されている内容は、この20年間で飛躍的に拡大した。
それに伴い、1本のゲームに携わる制作スタッフの数も増大し、現在ではスタッフロールに100人近い名前が並ぶことも珍しくない。
こうしたゲームの場合、先に挙げた4つの職種の中でもさらに役割が細分化され、例えば『操作方法を考える人』と『シナリオを考える人』が別の人である場合も多い。
さらに、『プロデュースをする会社』と『プログラムを組む会社』が異なる場合も多く、今後そういったケースがさらに増えると予想される。 |
|
|
| |
|
|