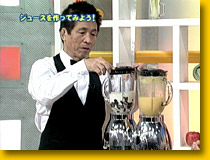| |
身近にあって、工作にもよく使われる『ゴム』。何といっても、あの伸び縮みする性質がおもしろい。
今回は、そんな『ゴム』を使って遊ぶ『ゴム銃』の作り方も教えちゃうぞ!
-Qっとくんが理解したこと- |
|
| |
| (1) |
『ゴム』は、木の樹液から作られている。『ゴムの木』は主に東南アジアで栽培されていて、木の幹にキズをつけて樹液を採集するのだ。
樹液を固めただけの『生ゴム』は弾力性が弱く、切れやすい。しかし、『生ゴム』とイオウを混ぜ合わせて加熱すると、強い『ゴム』になるのだ。 |
| (2) |
『ゴム』の弾力を活かしたおもちゃはいろいろあるけど、なかでも手軽に作れて楽しいのが、『輪ゴム』で作る『ゴム銃』だ。
『ゴム銃』は、割りばし5本と輪ゴム7本だけで作ることができる。引き金は、ゴムの弾力によって、引いた後必ず元に戻るように作るのだ。 |
| (3) |
『ゴム銃』は、体力に関係なく、こどもから大人まで一緒になって楽しめる。
そんな『ゴム銃』の楽しさを知ってもらうために、『ゴム銃』の射撃大会が行なわれているのだ。射撃大会では、遠くの的をじっくり狙う種目や、スピードが要求される種目などが行なわれている。 |
|
|
| |
-プラスあるふぁ- |
|
| |
 |
ゴムの歴史は古く、6世紀のアステカ文明で天然ゴムが使われていた痕跡がある。
アステカや、11世紀のマヤ文明においても、ゴムは『弾力を活かしたおもちゃ』として使われていたようで、コロンブスが1493年出発の航海でジャマイカに上陸したときに、原住民がゴムの球をけって遊んでいたのを見たことで、ゴムの存在がヨーロッパでも知られるようになったのだ。
なお、ゴムが工業製品として重要視されるようになったのは、加硫ゴムの発明 (グッドイヤー:1839年)、空気入りタイヤの登場(ダンロップ:1887年)を経てからのことである。 |
|
|
| |
|
|