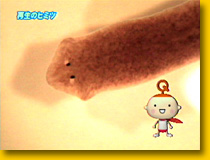| |
鉄にくっついたり、同じ極どうしだと反発したり。『磁石』って何だか不思議だよね。でも、磁石は毎日の暮らしをいろんな所で支えているんだよ。
今回は、いろんな角度から磁石について解説するよ!
-Qっとくんが理解したこと- |
|
| |
| (1) |
磁石にはN極とS極があり、違う極同士はくっつき、同じ極同士は反発しあうのは皆も知っていると思うが、鉄などを引きつける磁石の力のことを「磁力」という。
磁石を細かく砕き、しっかり振ると、くっつかなくなる。バラバラだとそれぞれが磁力を打ち消しあうためである。
だが、この磁石に別の磁石をくっつけてから試してみると、元どおりの磁石の役割を果たす。
これは、細かな磁石の中のN極とS極を整列させることで、それぞれの磁力が一つの方向を向いて、磁石の役割が戻るからなのだ。 |
| (2) |
磁力は電気とも密接な関係がある。巻いたコイルを磁石のそばに置き、磁石を回転させると、横にあるコイルに電流が流れるのだ。
磁石が動いて電気を生み出すこの現象を「ファラデーの電磁誘導」という。タイヤが回転して自転車のライトが点くのも、このしくみを利用している。 |
| (3) |
身のまわりで一番身近な磁石は地球である。それを表しているのがオーロラ現象だ。
太陽から飛んでくる、電気を持った小さな陽子や電子は、地球の持っている磁力に引っ張られ、地球の磁力線に沿って、北極や南極の大気に流れ込んでくる。
そのとき、大気の中の酸素や窒素が光る。これがオーロラなのだ。 |
|
|
| |
-プラスあるふぁ- |
|
| |
 |
家電製品において、モーターやスピーカーなどに用いられる磁石だが、それらのものを小型化するためには、より強力な磁石が欠かせない。
現在使われている磁石で最も強力なものは、『ネオジム』や『サマリウム』といった希土(きど)類を使った磁石である。
希土類元素の存在や役割については、一昔前までは十分に知られておらず、「稀な存在」という意味で『稀土類』と表記されていた。
しかし、技術の進歩に磁石が重要な位置を占めるようになってきた今、「希望」の字が当てられるようになったのである。 |
|
|
| |
|
|